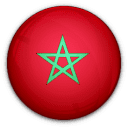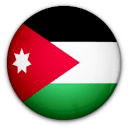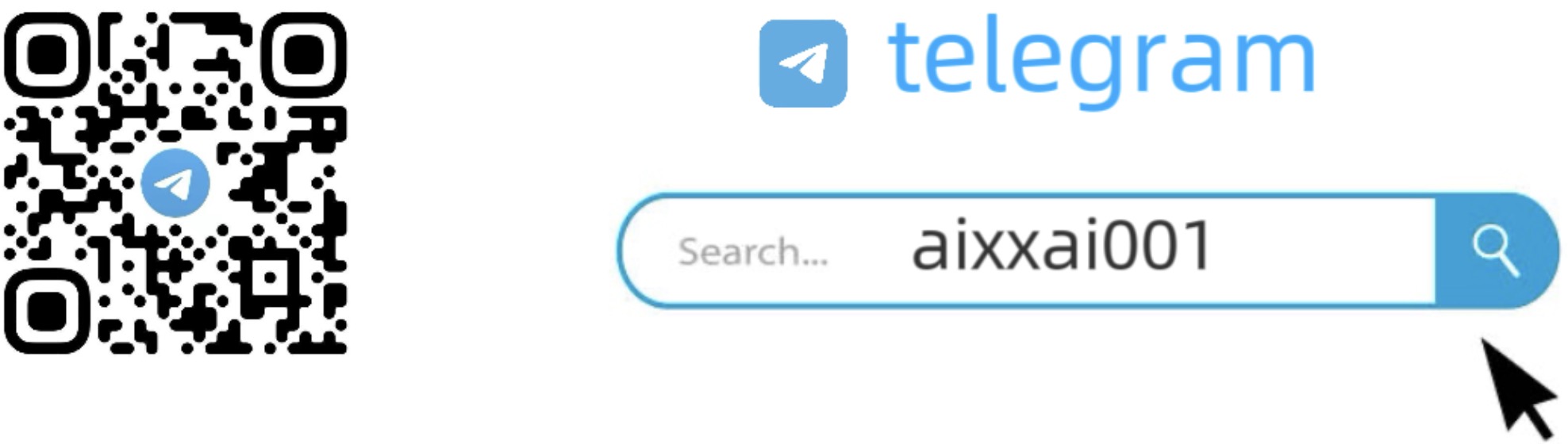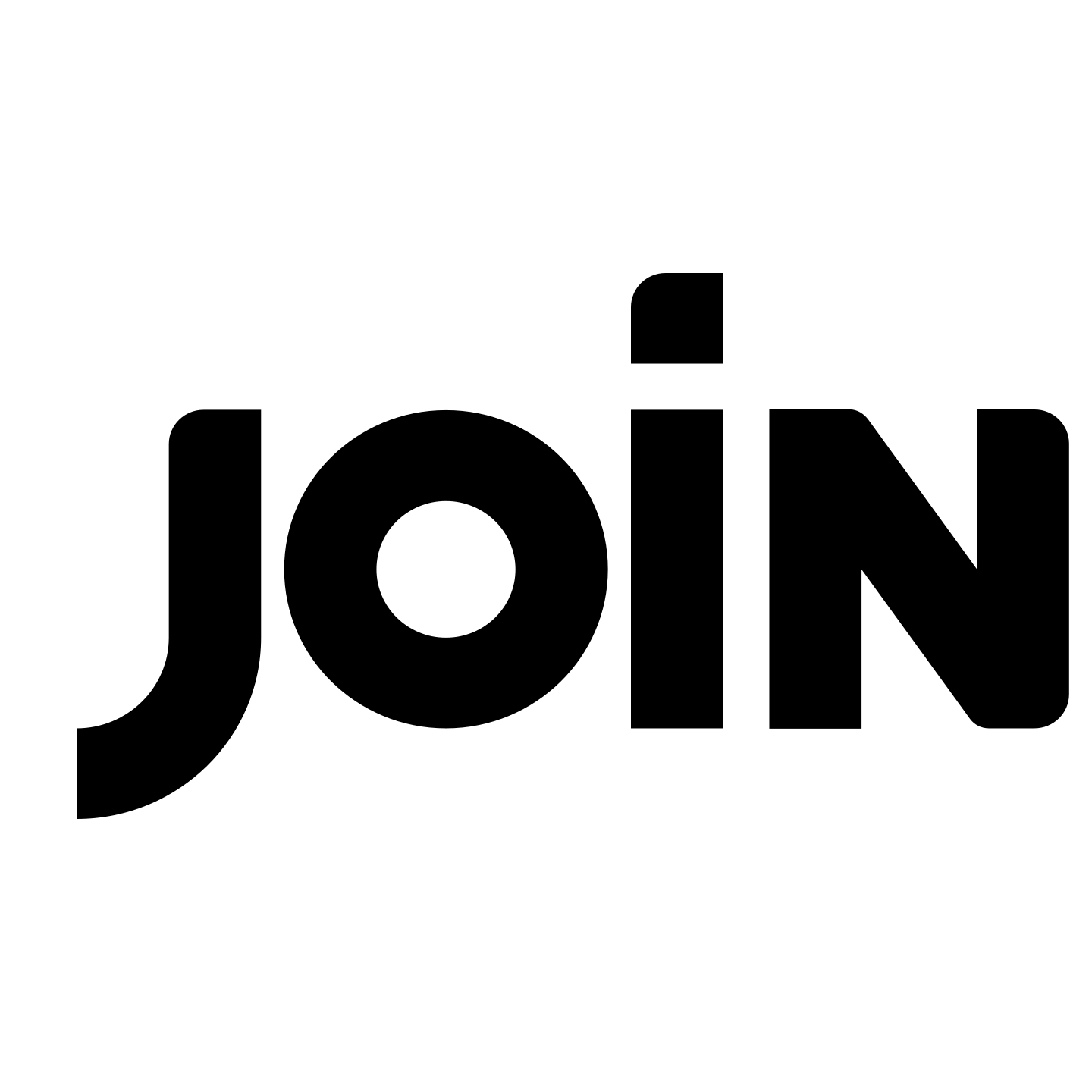高校野球の「球数制限」と「7 回制」が選手の成長に与える影響
高校野球のルール変更で、球数制限と 7 回制が導入された。これらの制度が選手の成長に与える影響について解説する。

高校野球のルール変更
高校野球のルールが変更され、野球自体が大きく変わろうとしている。その象徴が、2021 年のセンバツ大会から設けられた「球数制限」や 2024 年の春のセンバツから導入された「低反発バット」だろう。さらに、昨年から高校球児の負担を考慮し、「7 回制」の議論も話題になっている。
球数制限の影響
球数制限は選手育成にも影響しており、普段の練習から球数が管理されていることで、投げるためのスタミナを鍛えにくくなっている。そのため、実戦で練習以上の球数を超えた場合は、踏ん張りきれず大崩れをしてしまう可能性も高くなる。さらに、練習の時点で負荷をかけないため、緊張感のある実戦でパフォーマンスが発揮できなくなることや、本来なら怪我するまでにもいかない球数で怪我をすることもあるという。
継投策のデメリット
この影響で 4~5 人の選手を 1 試合に投げさせる戦略が主流化する兆しは、すでに見えはじめている。しかし、この継投策にもデメリットはある。前述したことに加え、仮に高校野球で短いイニングが主流化すると、将来的に大学野球やプロ野球で先発投手として長いイニングを投げられる投手が減る可能性もある。
「投げなさすぎ」の弊害
さらに、球数制限による問題のみならず、2019 年の夏の岩手県予選の決勝では大船渡高校が佐々木朗希(現・ロサンゼルス・ドジャース)を投げさせないということも話題になった。このケースのように将来有望株の投手は大事な試合になっても温存する実例は今後増えていくことが予想される。
結論
高校野球においてはよく「投げすぎ」による問題が取りざたされるが、今は「投げなさすぎ」も投手を苦しめるのである。複数の投手を投げさせることが当たり前になった現代の高校野球において勝ち上がるカギは、それぞれの投手の調整能力にかかっているとも言えるだろう。